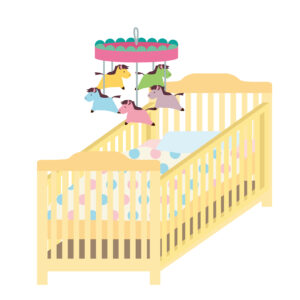テーブルに食事を並べると、それまで遊んでいた子どもも遊びを中断して、嬉しそうに駆け寄ってきますよね。
でもいざ食べ始めると、ダラダラ食べたり、食事を箸でツンツンつついたり。
子どもの遊び食べに困っているお母さんも多くいらっしゃるのではないでしょうか。
食事を残されたり、食事で遊ばれたりすると「せっかくつくったのに・・・」と落ち込みますよね。
なぜ、子どもは遊び食べをするのでしょうか。
子どもが遊び食べする原因と対処法を紹介します。
目次
子どもが遊び食べする原因

なぜ、子どもは遊び食べするのでしょうか。
子どもが遊び食べする原因をみていきましょう。
1.お腹が空いていない
お母さんはお腹が空いていない時に、何か食べますか?
「後で食べよう」「軽食で済ませよう」と考えたことはありませんか?
反対に、お腹が空いている時には「とりあえず、何か食べよう」と思って、好きじゃないものであっても食べたことがあるのではないでしょうか。
またその食事の前に、しばらく何も食べていなくても、お腹が空いていないということはありませんか?
特に便秘が続いている日はお腹が張って苦しく、空腹に感じないお母さんも多くいらっしゃると思います。
お腹が空いていると、好きなものはもちろん、好きじゃないもの、嫌いなものであっても、口に運んで食べようとします。
そう考えると、お腹が空いていなければ、好きなものだけを食べて、
「ごちそうさま!」と言いたくなる子どもの気持ちも分かるのではないでしょうか。
子どもがお腹を空かせている、空かせていないというのは、どのように判断すればいいのでしょうか。
判断するためには、2つのポイントがあります。
その食事の前に食べた量
お昼ごはんをたくさん食べたり、おやつを食べたりすると、夜ごはんの時間になってもお腹が空かない可能性があります。
またジュースや牛乳を飲んだら、水分だけでお腹がいっぱいになります。
もし、子どもの遊び食べが始まって「お腹が空いていないのかな?」と思ったら、
その食事の前の食事量を振り返ってみてください。
排便量
年齢や身体の大きさによって、子どもの排便のペースはさまざま。
個人差があるので、何日排便していなければ便秘だという決まりはありませんが、便がたまるとお腹が張ってきます。お腹を触って、張っているようであれば、ここ数日の排便の有無を振り返ってみてください。
私には4歳、1歳半の子どもがいます。上の子は3歳になった頃に、時々遊び食べをしていました。
「おやつも食べさせていないのに、どうして食べないんだろう?」と疑問に感じて、お腹を触ってみました。
すると、食事もおやつも食べていないのに、お腹がパンパンに張っていることに気付きました。
毎日、便は出ていましたが、量が少なかったんです。排便があっても、量が十分出ていなければ、お腹が張って、お腹が空かないかもしれません。
2.お腹が途中でいっぱいになった
小腹が空いている程度では「そんなに食べなくてもいいかな」と思うこともありますよね。お腹があまり空いていなければ、用意した食事を全部食べ終わる前に、途中でお腹がいっぱいになることがあります。
また、「バイキングでたくさん食べるなら、食べ始めてから20分間がカギ」と聞いたことはありませんか?
これは食べ物が胃に入ってから、満腹中枢が刺激され、脳に伝わるのに20分間かかるからです。
もし食べ始めて20分経っていたら、あまり食べていなくても、満腹だと感じているのかもしれません。
食事の開始時間を覚えおいて、遊び食べをし始めたら、食べ始めてからどれぐらい経っているかをチェックしてみてください。
3.嫌いなものを食べたくない
「朝ごはんはパンにしたから、お昼ごはんはご飯にしよう」
「昨日は魚を食べたから、今日はお肉を食べよう」など、献立を工夫するお母さんも多くいらっしゃると思います。
毎食、栄養バランスを考えて、料理するのは大変ですよね。
でも、子どもはお母さんのそんな苦労を知らず、嫌いなものを食べたがりません。
好き嫌いする子どもは、嫌いなものが目の前にずらりと並ぶと、「食べたくないものがたくさんある」と思って、食べる気を失って、箸を止めてしまいます。
4.気が散っている
子どもに絵本を読み聞かせする時にテレビをつけていると、子どもは絵本ではなく、テレビに注目してしまいますよね。
食事も同じです。
目の前に美味しそうな料理が並んでも、動かない料理より音が鳴ったり、画面が動いたりするテレビに注目してしまいます。
大人であれば、テレビを見ながら、箸で食べ物をつまんで、口に運んで食べられます。
でも箸やフォーク、スプーンなどの扱いに慣れていない子どもは、テレビを見ながら上手に食べることができません。
中には、食器を使って、テレビ番組の真似をする子どももいます。
遊び食べが始まったら、子どもが何を見ているか? 何を考えているか?
子どもをよく観察してみましょう。
子どもの遊び食べの対処法

子どもの遊び食べをやめさせるには、どうしたらいいのでしょうか。
子どもの遊び食べの対処法をみていきましょう。
1.お腹を空かせる
お腹が空いていないなら、お腹を空かせましょう。
お腹を空かせる方法は2つあります。
身体を動かす
お腹を空かせて、子どもにご飯をしっかり食べてもらうためには、身体をいっぱい動かすことが大事です。幼稚園や保育園に通っていると、身体を動かす機会はたくさんあります。
でも、未就園児であれば、お母さんが子どもを公園に連れ出したり、散歩したりさせる必要があります。
家の近くに公園があるなら、子どもを公園に連れて行って、滑り台や鉄棒などで遊ばせましょう。
ブランコやシーソーでもかまいませんが、滑り台や鉄棒などで遊ばせるほうが、身体をいっぱい動かすことができます。
私は子どもを連れて、公園によく行きますが、遊んでいる子どもを見ずに、ずっとスマホを触っているお母さんをよくみかけます。子どもが公園で遊んでいる間、暇に感じるお母さんもいらっしゃるかもしれません。
でも、ベンチに座って子どもを見守ったり、子どもが滑り台で滑っている姿をスマホで撮影したりすると、お母さんも楽しめますよ。
また、家の近くに公園がないなら、スーパーまで歩いて行ってみましょう。
もし、歩いて行けるスーパーがないなら、広いショッピングモールに行って、子どもと一緒に歩きましょう。子どもがショッピングカートに乗り慣れていると、カートに乗りたがるかもしれませんが、それでは身体を動かしたことにはなりません。
私は子どもがカートに乗りたがったり、抱っこをせがんだりしたら、「おもちゃコーナーまで歩いて行こうか」と言って、手をつないで歩いています。子どもが大好きでワクワクするような場所に向かえば、子どもも楽しんで歩くようになりますよ。
おやつを食べさせない
毎日、おやつを食べる習慣がついている子どもは、おやつの時間をなくすと、ぐずってしまうかもしれませんね。おやつを食べる習慣がついているなら、おやつの量を減らしてみましょう。
おやつの量を減らしても、食事の時間までにお腹が空かないなら、おやつの時間を早めてみてください。
また、食べさせるおやつの種類を変えてみてもいいかもしれません。
チョコレートやクリームが含まれている甘いおやつは、お腹に長時間残ります。
クラッカーやキャンディなど、カロリーが低く、糖分が抑えられているおやつをあげましょう。
2.嫌いなものをたくさん出さない
子どもの健康や成長を考えると、好きな食べものだけでなく、嫌いな食べものもバランス良く食べてほしいですよね。
栄養バランスを気にするあまり、お母さんがよくつくるのが、野菜をたくさん使った食事です。
お母さんは子どもが食べやすいように工夫したつもりでも、子どもは「こんなにたくさん食べるのは嫌だ」と思ってしまいます。
子どもが嫌いな食べものは少なめにして、まずは食べられるようにしましょう。
食べられたら、明日、明後日と、子どもが気づかない程度に、少しずつ量を増やしていきましょう。
3.デザートで釣る
私の子どもは果物が好きで、毎食後、必ず果物を食べたがります。
そこで、ごはんを残したら「お腹がいっぱいなんだから、果物は食べられないよね」と言って、
用意していた果物をさげています。
ご褒美で釣るようで、この方法がいいのか、悪いのかは分かりませんが、子どもはごはんを全部食べられるようになりました。
私の友人は、子どもにお菓子をわざと見せて、「ごはんを全部食べられないのに、お菓子はいらないよね」と言って、お菓子を棚に片付けているそうです。
4.食事に集中できる環境をつくる
子どもが食事に集中できるように、テレビを消したり、絵本やおもちゃを見えないように片付けたりしましょう。
我が家はリビングで食事するんですが、リビングには、テレビはもちろん、おもちゃや絵本など、子どもの大好きな物がたくさんあります。
子どもが遊び食べをしていた頃、テーブルに食事を並べると、子どもは椅子に座って、手を合わせて、ちゃんと「いただきます」と言っていましたが、食べ始めてしばらくすると、子どもの手が止まりました。
「テレビをつけているからかな」と思って、テレビを消すと、子どもの視線はテレビから絵本が片付けられている本棚に。
子どもは本棚をみつめて、「ノンタンがいるね」「はらぺこあおむしを読もう」と言いました。
そこで、本棚にカーテンを取り付けて、絵本が見えないようにしたところ、次は視線がおもちゃの棚に。
仕方なく、おもちゃの棚にもカーテンを取り付けたところ、やっと食事に視線が向くようになりました。
食べ終わったら、もちろん、絵本を読み聞かせて、おもちゃで一緒に遊びます。
でも、食事の時間、絵本を読む時間、遊ぶ時間、テレビを見る時間と、時間を区切ってメリハリをつけることで、食事を含めて物事に集中できるようになりますよ。
5.時間がきたら、お皿をさげる
お腹が空いていないのに、またあまり食べたくないのに、テーブルに食事がいつまでも並んでいると、子どもはダラダラ食べてしまいます。
ダラダラ食べないように、30分で食べるなど、食事の時間を決めましょう。
食事の時間を短くするなら、突然短くするのではなく、徐々に短くしてください。
今まで1時間かけて食べていたのに、突然30分で食べるように言われると、子どもは戸惑ってしまいます。
一日10分ずつ早く切り上げて「今日は50分間で食べる」「明日は40分間で食べる」「明後日は30分間で食べる」と、食事の時間を段階的に短くしていきましょう。
食事の時間を決めて、その時間がきたら食事が残っていても、お皿をさげてください。
「お腹がいっぱいなのかな?」と思って「もう、ごちそうさまする?」と聞くと、「まだ食べる」と言われ、このやり取りを繰り返して、ダラダラ食べていました。
「このままやり取りを繰り返していては、ダラダラ食べるのが癖になってしまう!」と思いました。
そこで、時計を指して「20時になったら、ごちそうさまをしようね」と言って、時間がきたらお皿をさげました。
すると、子どもは「本当にごちそうさまをしないといけないんだ!」と気付いて、時間内に食べ終えるようになりました。
栄養バランスを考えて食事をつくったお母さんとしては、ダラダラ食べてでも、残さずに食べてほしいのが本音だと思います。
でも、幼稚園や小学校などで、お弁当や給食を1時間かけて食べることはできませんよね。
子どものためにも、思い切ってお皿をさげてくださいね。
まとめ

子どもが遊び食べする原因対処法を紹介しました。
子どもが遊び食べする原因には、
・お腹が空いていない
・お腹が途中でいっぱいになった
・嫌いなものを食べたくない
・気が散っている
などがあります。
子どもの様子をよく観察して、遊び食べをする原因を突き止めましょう。
また、遊び食べの対処法には、
・お腹を空かせる
・嫌いなものをたくさん出さない
・デザートで釣る
・食事に集中できる環境をつくる
・時間がきたら、お皿をさげる
などがあります。
遊び食べが長期間続くと、子どもが食べ物で遊ぶ習慣を身につけてしまいます。
子どもの遊び食べに気づいたら、できるだけ早めにやめさせましょう。